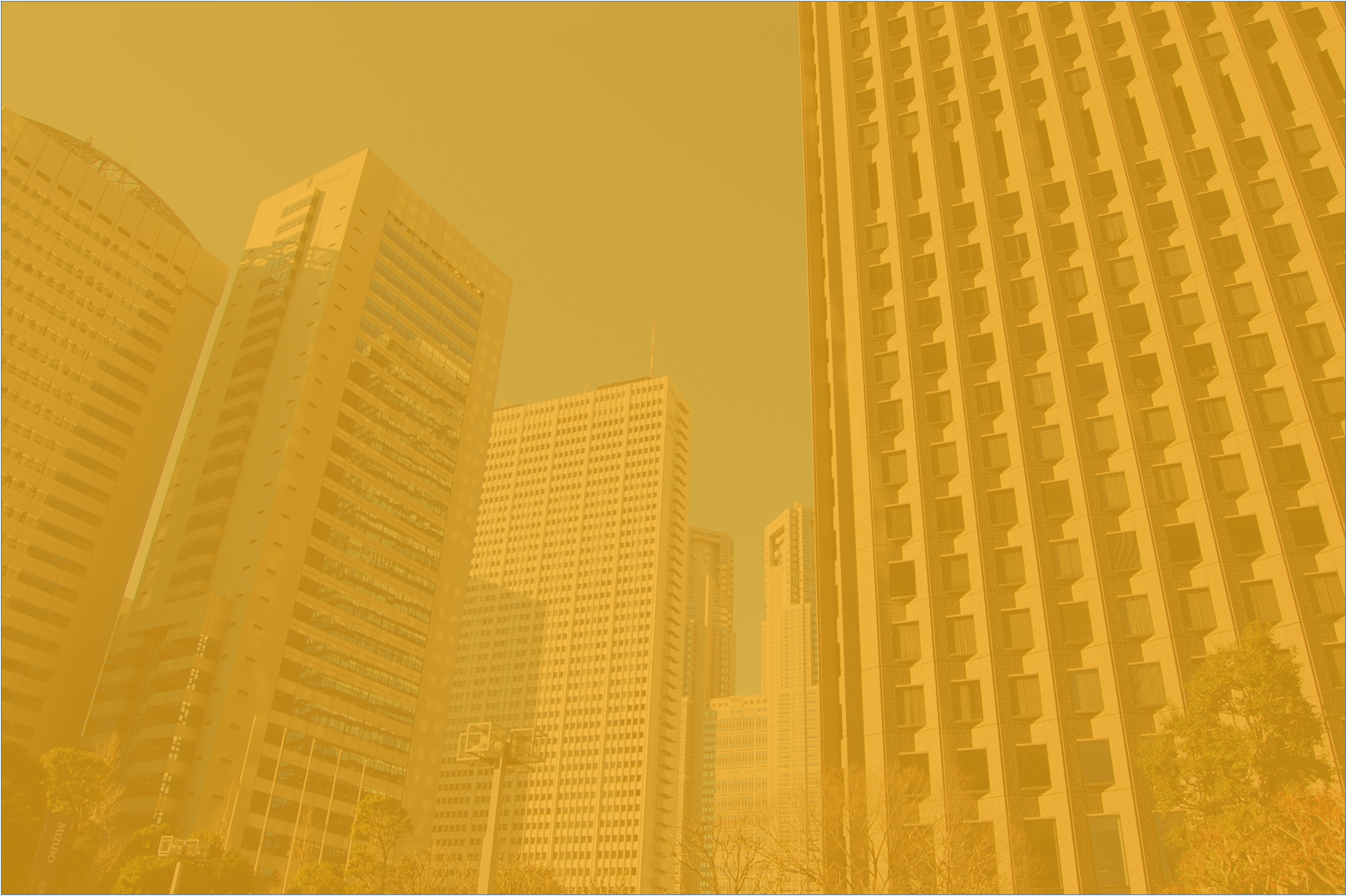企業の経営者が営業職を雇用する際、どのくらいの給料を支給すればよいのか気になるところです。営業職は仕事の成果によって企業への貢献度が大きく変わってきます。そのため、支給額の決定に迷いが生じてしまうケースも少なくありません。営業職では、歩合給制度を取り入れて支給する給料を決めているのが通常です。歩合給制度によって給料額を決めれば、仕事の成果に見合った額を支給できるからです。そこで、経営者が社内の営業職に支給すべき給料額について考えてみましょう。
把握しておくべき営業職の平均給料や手取りは?
企業の社員がもらえる給料額は、どの業界でもある程度相場が決まっています。営業職においてもそれは例外ではありません。したがって、経営者側は、営業職の平均的な給料額を基準にすれば無難に支給額を決定できるでしょう。営業職の平均的な給料額は、年齢層によって違います。具体的には、20代が15万円、30代が25万円、40代が35万円程度です。会社員の場合は、給料から各種税金や保険料が一定額控除されます。そのため、営業職の手取りの給料額は、12~30万円程度です。ただ、営業職の場合、仕事の成果によってもらえる給料額も変動するケースが少なくありません。したがって、優秀な営業職であれば、年収1000万円以上を得ている人がいる一方、平均給料よりも少ない人も存在します。
歩合給制度を取り入れる際に考えるべき問題点
営業職の場合、仕事の成果が具体的な数字であらわれる職種です。営業職の給料額を決める際、歩合給制度を取り入れるとよいでしょう。それにより、社員のモチベーションアップにつながりやすくなります。企業の中には、営業職の給料額の算定に歩合給制度を取り入れているところが少なくありません。歩合給制度を取り入れる場合、営業職の仕事の成果に見合った給料額が支給できるようにすることが大切です。具体的には、売上よりも利益を基準に歩合計算の方法を決めるようにします。経費が大きければ売上が多くてもあまり利益が発生しません。売上を基準に歩合計算をすると、そのような状況にもかかわらず歩合給が発生してしまうという問題が生じます。したがって、企業に利益が出た段階ではじめて歩合給が発生するような形で歩合計算を定めたほうがよいのです。また、歩合計算の方法を決める際、保証給を高く設定しすぎないようにしましょう。保証給が高いとそれだけで十分な収入を得られてしまいます。それにより、歩合給がなくても問題なくなるので、頑張って仕事をする必要もないという考えを持つ人が出てきてしまうのです。例えば、給料額は月間にあげた利益の20%で、保証給が20万円だったとします。このようなケースでは、月間の営業の成果がゼロでも20万円の給料を受け取れてしまいます。歩合給制度を取り入れる際、この問題点についても考えなければなりません。
歩合給制度を効果的に取り入れるための策は?
保証給が高いと、複数の月のうち、ある月に売上や利益を集中させてより多くの歩合給を獲得できてしまうという問題も発生します。例えば、ある2カ月間の売上が500万円、利益が200万円で、歩合の基準は月間にあげた利益の20%、保証給が20万円とします。この場合、2カ月間とも売上が250万円ずつ、利益が100万円であれば、2カ月分の給料は40万円です。一方、最初の月の売上が100万円で利益が40万円、次の月の売上が400万円で利益が160万円である場合、2カ月分の給料は52万円になります。したがって、このような問題を解消できる歩合計算の方法を取り入れなければなりません。その対策方法はいくつか考えられます。まず、数カ月単位の歩合計算にすることです。例えば、3カ月間の歩合計算をし、その額を次の3カ月分の給料に反映させるのです。ある月の歩合計算が保証額を下回るとき、その後数カ月間は持ち越しにする方法も考えられます。上記の例で、ある月の歩合給が5万円である場合、保証給の20万円より15万円下回ります。そのようなとき、次の月の歩合計算が30万円であったとすると、そこから15万円を差し引いた15万円を給料額とするのです。それから、仕事の成果を給料ではなく、賞与として反映させる方法も考えられます。
社員が意欲的になれるベストな給料体制にしよう
社員が意欲的に仕事をする環境を作るために、営業職の給料体制に歩合給制度を取り入れるのは適した方法です。しかし、設定する内容を誤ってしまうと、逆効果になってしまうケースも少なくありません。歩合給制度を取り入れる場合、社員1人1人が仕事を頑張ろうと思える程度の適度な歩合を定めることが重要になります。